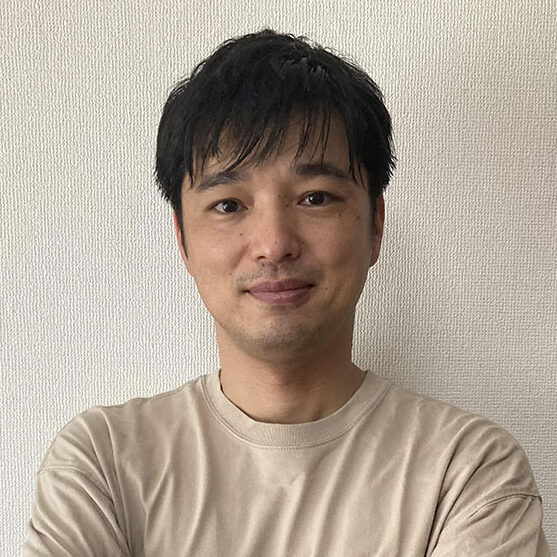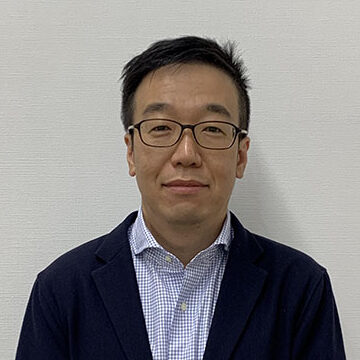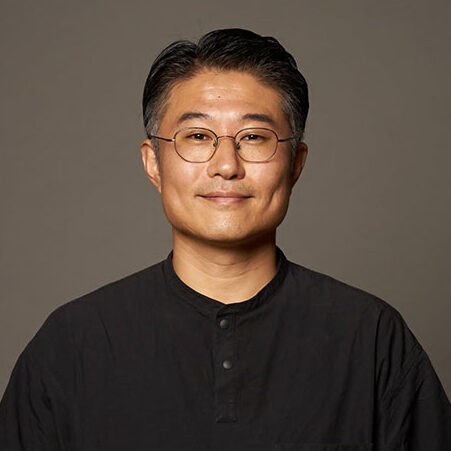このたび、懐徳総研主催による「第1回 次世代自治共創会議」が無事に終了いたしましたことをご報告申し上げます。

場所:
東京大学本郷キャンパス山上会館
(オンライン配信あり)
日程:
2025年5月31日(土) 13:30〜18:00
(開場13:00)
内容
基礎自治体が抱える主要課題への対応について、先進事例の紹介・分析とアイディア提供を行う。
- 鈴木寛先生による基調講演(小規模自治体の課題と懐徳総研の使命)
- 研究部会別報告
- 教育・学校部会
- 防災部会
- 自治体DX・AI部会
- 健康・医療部会
3. 小規模自治体の今後を巡るパネルディスカッション
プログラム ※右端の三角マークを押すと、内容の要約をみることができます。
13:30 基調講演 「田園に根ざしたウェルビーイング—共創と自治の新たな可能性—」
鈴木寛(東京大学公共政策大学院教授、慶應大学特任教授、元文部科学副大臣)
・GDPを超えた価値観の重要性
国連も提唱する「Beyond GDP」の考え方に基づき、経済的豊かさだけでなく、真の幸福(ウェルビーイング)を追求する社会への転換を提唱。明治維新が薩長土肥という「辺境」から始まったように、現代の変革もまた地方から始まると指摘した。
・5万人以下の自治体のポテンシャル
日本の市町村の約69.3%(1,216自治体)を占める。人口の合計は約2,000万人で、オーストラリアや台湾の国家人口に匹敵する。日本の食料生産の55.8%、水源の約9割、自衛隊基地の殆どを担い、国の安全保障の根幹を支える重要な存在である。
・新たな連携「メタバース役場」構想
従来の合併や連携中枢都市圏といった枠組みの限界を指摘。地理的に離れた自治体同士がコンソーシアムを組み、教育・健康・農業などの分野ごとに柔軟に連携する「未来型結(みらいがたゆい)」や「メタバース役場」を提唱。これにより、人材や農機具といった資源の効率的な共有が可能になるとした。
・懐徳総研の役割
すずかんゼミのOB/OGが中心となり、幸福の再定義と、それを実現するための実践的な地域課題解決を支援するために設立された。
14:00 研究部会別報告
教育・学校部会 「須崎市(人口2万人)の教育改革—さいたま市改革メソッドの地方展開—」
細田眞由美(前さいたま市教育長、兵庫教育大学客員教授、うらわ美術館館長、須崎市教育政策プロデューサー、一般社団法人LEAP理事)
・さいたま市での実績
人口135万人の大規模自治体にて、「3つのG(Grit:やり抜く力、Growth:学び続ける/成長し続ける力、Global:グローバルなコミュニケーション能力を身につけグローバル人材となる)」をスローガンに教育改革を断行。英語力5年連続日本一などの成果を上げた。
・小規模自治体での挑戦
高知県須崎市(人口約2万人)の教育改革に参画。「さいたま市でできたことは須崎市でもできる。むしろ小規模だからこそ質の高い教育を『全員に』『0歳から』提供できる」とその可能性を強調。
・須崎市のビジョン「Make “IT” Fun」
「好きなこと(it)を楽しむ(Fun)」と「情報技術(IT)の活用」のダブルミーニングを込めた。
「楽しくなければ学びじゃない」をキーワードに、子どもたちの主体性を引き出す。
・改革成功の4つのポイント
1. 外部人材と「翻訳者」
首長が覚悟を決めて外部人材を登用し、その専門的な言葉を現場に伝える「翻訳者」のいる組織を構築することが極めて重要。
2. 具体と抽象の往還
日々の具体的な業務と、「日本の未来の教育課題を解決する」という抽象的なビジョンとを常に関連付けて語り、職員のマインドを醸成する。
3. すさきデザイン
地域全体(大人たち)を巻き込み、子どもたちのための豊かな体験を共同で創出する。
4. 楽しむ姿勢
土佐弁で「調子に乗る」を意味する「ほげる!」を合言葉に、改革者である大人自身が楽しむことが、子どもや大人の学びの相乗効果を生むと説いた。
防災部会 「熊本県の防災DX—熊本地震・令和2年7月豪雨の経験から—」
和田大志(熊本県職員 知事公室危機管理防災課、対話型自治体経営シミュレーションゲーム開発者)
🔗当日の資料はこちらをクリック
・自治体経営シミュレーション
2030年の自治体を舞台に、限られた予算で課題解決の意思決定を行うロールプレイングゲーム「SIMULATION熊本2030」を開発。全国500以上の自治体で活用されている。
・熊本県の防災DXの取り組み
1. 東大・気象庁との連携
最新技術で過去の豪雨を精密に再現し、現実に即したシナリオで防災訓練を実施。
2. JAXAとの連携
災害前後の衛星画像をAIで比較分析し、夜間や広範囲でも建物の被害状況を迅速に推定する技術を開発。
3. 活動調整のデジタル化
災害対策本部での情報共有をホワイトボードからデジタルツールに移行し、物理的・時間的な制約を克服。
4. 防災DXの本質
本質は「限界突破」であると定義。予測能力、迅速な対応力、組織の対応容量といった、従来の限界を超えるための手段であると結論付けた。
自治体DX・AI部会 「AI革命で加速する自治体DX」
青木大和(株式会社パブリックテクノロジーズ 代表取締役CEO)
藤井靖史(福島県西会津町CDO、ばんだい振興公社理事長、福島県川内町・広野町、愛媛県宇和島市DXアドバイザー、総務省地域情報化アドバイザー)
🔗当日の資料(スライド①青木大和)はこちらをクリック
🔗当日の資料(スライド②藤井靖史)はこちらをクリック
青木 大和 氏
・日本のデジタル赤字とAI革命
日本は、米国の巨大テック企業・プラットフォーマーの影響により、デジタル分野で約7兆円の貿易赤字を抱えている。インターネット革命には乗り遅れたが、AI革命は大きなチャンスであると強調。
・行政特化AI「パブテクAI行政」
現場の職員からの「自分たちの業務を改善してほしい」という提案をきっかけに共同開発された、行政に特化したAIエージェント。対話を通じて企画書作成などを支援し、将来的には電話応対の自動化も目指す。
藤井 靖史 氏
・DXの本質と自治体の現状
DXは技術導入(Digital)よりも変革(Transformation)が重要。しかし、多くの自治体ではノンコア業務が7割を占め、人材不足から変革に踏み出せない現状があると分析。
・AIの役割と可能性
膨大な「情報」を人間が理解できる「知識」へと整理するツール。日々の業務をログとして記録・データ化しAIに学習させることで、業務の引き継ぎやトラブル予測が可能になるとした。
・AI時代の人間
AIが普及することで、「何のためにそれを行うのか」という人間の本質や、住民と直接対話する「身体性」がより重要になると述べた。
健康・医療部会 「専門職と行政職員が共創する健康づくり」
ファシリテーター・荒川裕貴(横浜市立大学医学部公衆衛生学教室助教、東京大学公共政策大学院特任助教、一般社団法人Next Public Health Lab代表理事)
坪倉正治(南相馬市立総合病院地域医療研究センター長、南相馬市放射線健康対策委員会委員、相馬市健康対策専門部会委員、福島県立医科大学放射線健康管理学講座教授)
須田万勢(茅野市DX推進課DX 企画幹(リードアーキテクト)、組合立諏訪中央病院リウマチ膠原病内科医長、一般社団法人統合医療チームJIN代表理事)
16:50 パネルディスカッション 「自治体バージョンアップの方法論」
ファシリテーター・鈴木寛
髙島崚輔(芦屋市長)
青木大和(株式会社パブリックテクノロジーズ 代表取締役CEO)
矢部佳宏(ランドスケープアーキテクト、西会津国際芸術村ディレクター、一般社団法人BOOT代表理事)
・外部人材との協働
高島市長(芦屋市)
まずは内部職員の思いを引き出し、機が熟した段階で外部の専門家と繋ぐアプローチを実践。「モデル校」制度を廃止し、教員一人ひとりの「やりたいこと」を応援する形に変えた結果、教員と生徒双方の主体性が劇的に向上した。
矢部氏(西会津町)
外部人材が活躍するには、地域の深い文脈を理解し伝える「翻訳者」が不可欠。自身がその役割を担うことで、西会津町に多くの若者が集まり、定着する好循環が生まれている。
・「モデル事業・横展開」からの脱却
従来の「国がモデル地域を指定し、その成功事例を他に広める」というトップダウン方式には限界がある。これからは、各地域・各個人が持つ問題意識や「やりたいこと」を起点とし、同時多発的に連携が生まれる「メッシュ型」の共創が重要になるとの認識で一致した。
・首長からの意見
御代田町:クレームを住民の願いの凝縮と捉え、ログ化して分析することの重要性を再認識。
西会津町:小規模自治体は外部人材の力なしには立ち行かない現実を共有。
秦野市:長年の課題解決が一巡した後の「積み上げる」フェーズの難しさに直面しており、政治そのものの進化が必要。
須崎市:教育を軸に、人口減少先進県からの脱却を目指す覚悟を表明。
- 17:45 懐徳総研からのお知らせ
- ・小規模自治体の人員体制とメタバース役場
・今後の部会活動について
- 18:00 交歓会
- 立食形式での名刺交換・懇親会を予定しております。
【学生報告会について】
当日は、10:00~11:30に同じ会場で、東京大学鈴木寛研究室所属の学生による研究報告会を開催いたしました。
研究報告会の様子もYoutubeにて公開しております。
登壇者一覧
- 基調講演
鈴木 寛
Suzuki hiroshi
東京大学公共政策大学院教授、慶應義塾大学特任教授、元文部科学副大臣
[ プロフィール ]
1986年東京大学法学部卒業。通商産業省、慶應義塾大学助教授を経て参議院議員(12年間)。
文部科学副大臣(二期)、文部科学大臣補佐官(四期)などを歴任。地域活性化、教育、医療、スポーツ、文化、科学技術イノベーションに関する政策づくりや各種プロデュースを中心に活動。現在、大阪大学招聘教授、千葉大学医学部客員教授、電通大学客員教授、福井大学客員教授、和歌山大学客員教授、神奈川県参与、神奈川県立保健福祉大学理事、Teach for All Global board member, 日本サッカー協会参与、NPO法人日本教育再興連盟代表理事(ROJE)、ウェルビーイング学会副代表理事なども務める。
- 教育・学校部会
細田 眞由美
Hosoda Mayumi
前さいたま市教育長、兵庫教育大学客員教授、うらわ美術館館長、須崎市教育政策プロデューサー、一般社団法人LEAP理事
[ プロフィール ]
1983年より埼玉県立高等学校で英語教諭を務めた後、埼玉県教育委員会指導主事、県立高校教頭、さいたま市教育委員会指導2課副参事を歴任。2013年からさいたま市立大宮北高等学校校長を務め、2017年から2023年までさいたま市教育委員会教育長として、文部科学省の「英語教育実施状況調査>中学生の英語力(都道府県・指定都市別)」4回連続日本一を実現した。グローバル社会を生き抜く力を重視した「さいたまメソッド」を、著書『世界基準の英語力: 全国トップクラスのさいたま市の教育は何が違うのか』にて公開。現在は、うらわ美術館館長、兵庫教育大学客員教授、東京大学公共政策大学院講師、文部科学省学校DX戦略アドバイザー、須崎市教育政策プロデューサーなど多方面で活躍中。
- 防災部会
和田 大志
Wada Taishi
熊本県職員 知事公室危機管理防災課、対話型自治体経営シミュレーションゲーム開発者
[ プロフィール ]
1980年熊本県生まれ。2004年熊本県入庁。土木、福祉、人材育成、水俣病関係の業務を経て、2015年から6年間、知事公室勤務(知事直属スタッフ)となり、平成28年熊本地震・令和2年7月豪雨の二つの災害を最前線で経験。その後は、漫画『ONE PIECE』と連携した復興プロジェクトも担当。2021年~2022年は東京大学公共政策大学院(すずかんゼミ所属)にて対話型自治体経営シミュレーションゲーム「SIMULATION熊本2030」を用いた高校生の政治的有効性感覚の醸成、主権者教育への活用について研究。2024年から現職。
2017年「地方公務員が本当にすごい!と思う地方公務員アワード」「第12回マニフェスト大賞 最優秀コミュニケーション戦略賞」受賞。
- 自治体DX・AI部会
- 青木大和氏(株式会社パブリックテクノロジーズ 代表取締役CEO)も登壇
藤井 靖史
Fujii Yasushi
福島県西会津町CDO、ばんだい振興公社理事長、福島県川内村・広野町、愛媛県宇和島市DXアドバイザー、総務省地域情報化アドバイザー
[ プロフィール ]
1977 年生まれ。京都府出身。経営学修士。国内企業や外資系企業での経験を経て、仙台で株式会社ピンポンプロダクションズを設立。代表取締役就任。 2012年にKLab株式会社とのM&Aを実施し、EXIT。会津大学産学イノベーションセンター准教授を経て、現在は西会津町CDO、ばんだい振興公社理事長を務めるほか、福島県川内村、広野町、愛媛県宇和島市のDXアドバイザーなど、複数自治体と共創を進めている。その他、総務省地域情報化アドバイザー、デジタル庁オープンデータ伝道師、Code for Japanフェロー、会津の暮らし研究室取締役として活動している。趣味はDIYで、築200年の古民家を改装しながら住んでいる。
- 健康・医療部会
荒川 裕貴
Arakawa Yuki
横浜市立大学医学部公衆衛生学教室助教、東京大学公共政策大学院特任助教、一般社団法人Next Public Health Lab代表理事
[ プロフィール ]
2011年金沢大学医学部卒業。東京都立多摩総合医療センターで臨床経験を積んだ後、東京大学公衆衛生大学院で公衆衛生学修士(専門職)、医学博士を取得。現在は「人のつながりと健康」をテーマに、横浜市立大学で社会的孤立や孤独感に関わる研究、医学部生への公衆衛生教育に携わる。また、横浜市で実施した産官学連携の社会実装PJTの経験を元に、公衆衛生専門職を中心としたチームNext Public Health Labを立ち上げ、自治体・企業と専門職が共に健康づくりのエビデンス創出と社会実装を行う体制を目指して活動中。2024年11月より東京大学公共政策大学院特任助教。
須田 万勢
Suda Masei
茅野市DX推進課DX 企画幹(リードアーキテクト)、組合立諏訪中央病院リウマチ膠原病内科医長、一般社団法人統合医療チームJIN代表理事
[ プロフィール ]
2009年東京大学医学部卒業。諏訪中央病院、聖路加国際病院リウマチ膠原病センターでの臨床経験を積み、2019年より諏訪中央病院現職。地域総合病院の第一線で勤務しながら、2022年より茅野市役所のDX推進課に出向し、デジタル技術を利用した茅野市民のよりよい健康づくりに携わる。デジタル田園健康特区に指定された同市において、これまでに遠隔医療相談アプリを活用した持続可能な小児オンラインかかりつけ医体制の構築や、養生 ×テレワークによる心身のストレスを軽減させるプログラムの開発などを行っている。
坪倉 正治
Tsubokura Masaharu
南相馬市立総合病院地域医療研究センター長、南相馬市放射線健康対策委員会委員、相馬市健康対策専門部会委員、福島県立医科大学放射線健康管理学講座教授
[ プロフィール ]
2006年東京大学医学部卒業。亀田総合病院、帝京大学ちば総合医療センター、都立駒込病院などで臨床経験を積む。2011年4月、福島第一原発事故に伴う放射線被曝の危険にさらされた福島県浜通り地域において、相馬市・南相馬市を中心に地域住民の内部被ばく検査や避難の長期化に伴う二次的な健康影響に関する調査に取り組んできた。2015年東大大学院医学系研究科博士課程修了。2020年6月1日、福島県立医科大学放射線健康管理学講座主任教授に就任。同年6月、福島県での支援活動に対して、安藤忠雄文化財団賞を受賞。
- パネルディスカッション
- ファシリテーター・鈴木寛氏
髙島 崚輔
Takashima Ryosuke
芦屋市長
[ プロフィール ]
1997年大阪生まれ。米ハーバード大学(環境工学専攻、環境科学・公共政策副専攻)卒業。 2016年から2023年まで(特非)グローバルな学びのコミュニティ・留学フェローシップ理事長。世界の課題を解決する未来のリーダーを育ててきた。特に、海外大学進学やまちづくりへの若者参画を支援。 2023年4月、兵庫県芦屋市長選挙で初当選。同年5月より現職、日本史上最年少市長となる。公立学校で「ちょうどの学び」を実現するために力を注ぎ、ユース世代をはじめ、幅広い世代との対話を中心にしたまちづくりに取り組む。文部科学省中央教育審議会専門委員(2025年〜)。
青木 大和
Aoki Yamato
(株)パブリックテクノロジーズ代表取締役CEO、アルペンスキーヤー(2022年北京パラリンピック日本代表)
[ プロフィール ]
2020年にパブリックテクノロジーズを設立。公共領域No.1をミッションに掲げ、地方自治体のAI/DX推進を行う。公共ライドシェアの配車システムなどを基軸としたスーパーアプリ「パブテク」を提供。またAIを活用した行政業務効率化サービス「パブテクAI行政」なども提供する。 プライベートでは、起業家とアスリートの二刀流として、2022年の北京パラリンピックに日本代表として初出場。2026年のミラノコルティナパラリンピックにてメダル獲得を目指す。2023年には、Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2023に選出。
矢部 佳宏
Yabe Yoshihiro
ランドスケープアーキテクト、西会津国際芸術村ディレクター、一般社団法人BOOT代表理事
[ プロフィール ]
西会津国際芸術村ディレクター。ランドスケープデザイナー。長岡造形大学大学院空間計画学専攻修了、カナダ・マニトバ大学大学院ランドスケープアーキテクチャー修士首席修了。上山良子ランドスケープデザイン研究所、Studio CLYNE(カナダ), NITA DESIGN GROUP(上海)等を経て、東日本大震災をきっかけに帰郷し、西会津町奥川の 360 年続く楢山集落を 19 代目として継承する。ランドスケープ・アーキテクトの視座でコミュニティの最小単位である集落からフラクタルに広がる世界の理解を試み、持続可能な故くて新しい未来の風土、暮らし、地域経済の生態系について探究・実践するNARAYAMA PLANETARY VILLAGE L.A.B.を立ち上げた。主なプロジェクトに、NIPPONIA 楢山集落、石高プロジェクトなど。
- 総合司会
大岩 央
Oiwa Hisa
政策シンクタンクPHP総研主任研究員、政府広報アドバイザー
[ プロフィール ]
2008年、大阪大学文学部卒業。同年、PHP研究所入社。副編集長を務めたPHP新書編集部で「世界の知性シリーズ」を創刊(累計60万部超)。2021年より現職、各種研究提言プロジェクトの企画運営を担当。2022年4月より、政府広報アドバイザー(官邸国際広報室委嘱)。文化庁企画審査委員、鳥取県庁事業審査委員、日本生産性本部モーニング・フォーラムコーディネーターなどを務める。主な担当提言書に『日本のナラティブ・パワー 「2025」とその先への戦略』、『官邸の作り方-政治主導時代の政権運営-』。
主催:東京大学鈴木寛研究室、株式会社懐徳総合研究所
共催:株式会社パブリックテクノロジーズ、一般社団法人LEAP、懐徳会